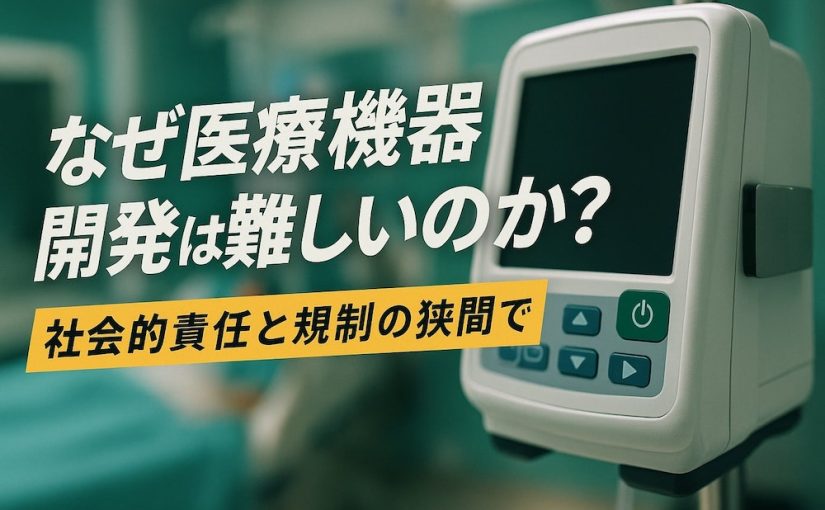「親父の会社は、腕は一流だったのに潰れました。」
兵庫の小さな工務店の三代目として生まれた私は、幼い頃から木材の香りと職人たちの活気に囲まれて育ちました。
親父の墨付けの正確さ、大工たちの鉋(かんな)がけの美しさは、今でも目に焼き付いています。
しかし、その会社はもうありません。
原因は、技術がなかったからじゃない。
「デジタル化の波に乗り遅れた」ただそれだけでした。
FAXでのやり取り、どんぶり勘定の経営、紙の図面…。
時代の変化が、私たちの誇りだったはずの技術を飲み込んでしまったのです。
この悔しさが、私の原点です。
株式会社BuildSync代表の杉原 悠真です。
今日は、私と同じように現場を愛し、未来を憂うあなたと一緒に、建設業界の今とこれからについて考えていきたいと思います。
「DXなんて、ウチみたいな中小企業には関係ない」
「ITは現場のぬくもりを奪う冷たいものだ」
もしあなたがそう感じているなら、この記事はきっとあなたのためのものです。
この記事を読み終える頃には、テクノロジーが現場の敵ではなく、むしろ職人の“手のぬくもり”を守るための最強の道具であることに気づくはずです。
さあ、泥の上から始まるDX革命の話を始めましょう。
なぜ今、建設業界にDX革命が必要なのか?
2024年問題と人手不足の深刻な現実
「また若いのが一人、辞めていったよ…」
先日お会いした地方の建設会社の社長が、寂しそうに呟いていました。
これは、決して他人事ではありません。
2024年4月から、建設業にも時間外労働の上限規制が適用されました。
これは「残業ありきで工期に間に合わせる」という、長年続いてきた業界の働き方が、いよいよ法的に通用しなくなったことを意味します。
さらに、人手不足は待ったなしの状況です。
建設業の有効求人倍率は常に高い水準で推移しており、特に現場の骨格を作る躯体工事の分野では7倍を超えることもあります。
これは、1人の求職者を7社で奪い合っている異常事態です。
その一方で、現場を支えてきたベテランたちは次々と引退していきます。
建設業就業者のうち、実に36%が55歳以上。
彼らが持つ熟練の技術や勘は、一体誰が受け継いでいくのでしょうか。
「技術はあるのに…」古い慣習が未来を蝕む
私の親父の工務店がそうでした。
技術力には絶対の自信がありましたし、お客様からの信頼も厚かった。
しかし、経営は常に火の車。
請求書は手書き、図面はすべて紙で管理し、現場との連絡はもっぱら電話。
「あの図面どこやったかな」「言った言わない」の繰り返しで、本来やらなくてもいいはずの作業に多くの時間が奪われていました。
結局、時代の変化に対応できず、黒字倒産という形で幕を閉じました。
この経験を通して、私は骨身にしみて理解したのです。
どんなに優れた技術も、それを支える「仕組み」が古ければ、砂上の楼閣に過ぎないのだと。
今、多くの建設会社が、かつての私の実家と同じ轍を踏みかねない状況にあります。
DXは“効率化”だけじゃない。現場の“誇り”を取り戻すための戦い
ここで私が伝えたいのは、DX(デジタルトランスフォーメーション)は単なるコスト削減や効率化の道具ではない、ということです。
もちろん、無駄をなくすことは重要です。
しかし、DXの本当の目的は、探し物や移動、手戻りといった付加価値を生まない作業から職人たちを解放し、彼らが本来の実力を発揮できる時間を生み出すことにあります。
若手は最新の技術でスマートに働き、ベテランは自身の経験をデータとして未来に残す。
テクノロジーは、現場から人間味を奪うのではなく、むしろ人間が人間らしく、誇りを持って働ける環境を取り戻すための戦いなのです。
建設DXの最前線!現場を変える3つのテクノロジー
では、具体的にどんなテクノロジーが現場を変え始めているのでしょうか。
難しく考える必要はありません。
ここでは、未来の現場の「三種の神器」とも言える3つの技術を、分かりやすくご紹介します。
BIM/CIM:3Dモデルで未来を“見える化”する
BIM(ビム)/CIM(シム)という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
これは、コンピューター上に建物の3Dモデルを作り、そこに設計からコスト、工程、維持管理に至るまでの、ありとあらゆる情報を詰め込んでしまう技術です。
これまで、私たちは何枚もの2Dの図面を見比べて、頭の中で立体を組み立てていました。
しかし、それではどうしても「図面では分からなかったけど、作ってみたら配管がぶつかった」といった手戻りが発生してしまいます。
BIM/CIMを使えば、建設前にコンピューター上で“建物を一度建ててみる”ことができます。
関係者全員が同じ3Dモデルを見ることで、認識のズレがなくなり、無駄な手戻りを劇的に減らすことができるのです。
これは、建設プロジェクト全体の「完璧な設計図」を手に入れるようなものです。
IoT:建機と職人が“会話”するスマートな現場
IoT(アイオーティー)とは、「モノのインターネット」のこと。
センサーを付けたモノが、インターネットを通じて情報をやり取りする技術です。
例えば、建設機械にセンサーを取り付ければ、事務所にいながら「今、どの機械がどこで動いているか」「燃料はあとどれくらいか」といった情報がリアルタイムで分かります。
職人のヘルメットにセンサーを付ければ、体調の急変や転倒を即座に検知し、事故を未然に防ぐことも可能です。
これまで現場監督が歩き回って確認していた情報が、自動的に集まってくる。
まるで、建機や道具、そして職人たちと直接“会話”できるような感覚です。
これにより、現場監督は管理業務から解放され、より創造的な仕事に時間を使えるようになります。
AI:熟練の“勘”をデータで次世代に継承する
AI(人工知能)は、もはやSFの世界の話ではありません。
建設業界でも、その活用が急速に進んでいます。
例えば、過去の膨大な工事データをAIに学習させることで、天候や周辺環境を考慮した最適な工事計画を自動で立案させることができます。
また、ドローンが撮影した現場写真をAIが解析し、「どこまで工事が進んでいるか」「危険な箇所はないか」を自動でチェックすることも可能です。
私が特に期待しているのは、技術継承への活用です。
一人のベテラン職人が引退すれば、その人が何十年もかけて培ってきた“勘”や“コツ”は失われてしまいます。
しかし、その動きや判断をデータとしてAIに学習させることができれば、それは会社の資産として残り続けます。
AIは、熟練の技を次世代に繋ぐ、最高の通訳者になり得るのです。
「ウチには無理…」は間違い!DX導入の失敗と成功の分かれ道
「なるほど、技術のすごさは分かった。でも、結局それは大手企業の話で、ウチみたいな会社には無理だよ」
そんな声が聞こえてきそうです。
実は、私自身がかつて、そう思わせてしまう大きな失敗を犯しました。
私が犯した大きな過ち:テクノロジーを“押し付けた”日々の記憶
BuildSyncを創業した当初、私は「こんなに素晴らしいシステムなのだから、導入すれば絶対に現場は良くなる」と信じて疑いませんでした。
最新の機能を詰め込んだ自社システムを、意気揚々と中小の施工会社に提案しました。
しかし、結果は惨憺たるものでした。
「ボタンが多すぎて、何を押せばいいか分からん」
「こんなものを覚える時間があったら、手を動かした方が早い」
現場からの反発は想像以上に強く、3社連続で契約を打ち切られてしまいました。
頭をガツンと殴られたような衝撃でした。
私は、画面の中のデータばかり見ていて、現場で泥にまみれて働く「人」の顔を見ていなかったのです。
その時、痛感しました。
現場はデータではなく、人で動いているのだ、と。
成功の鍵は“現場の声”から設計図を描くこと
その失敗から、私は方針を180度転換しました。
技術を“押し付ける”のではなく、“現場の声から設計する”という姿勢に切り替えたのです。
全国200社以上の建設会社を回り、職人さんや監督さん一人ひとりに話を聞きました。
「本当に困っていることは何か」「どんな機能があれば嬉しいか」「スマホの文字はどのくらいの大きさがベストか」。
そうして生まれたのは、機能を絞りに絞った、驚くほどシンプルなアプリでした。
成功の鍵は、いきなり完璧なシステムを目指さないことです。
まずは現場のたった一つの課題を解決することから始める。
その小さな成功体験が、現場の抵抗感を和らげ、次のステップへの足がかりとなるのです。
中小企業こそDXの恩恵を受けられる理由
高価なシステムや専門のIT担当者が必要だと思っていませんか?
それは大きな誤解です。
今や、スマートフォン一つで使える安価で高性能なクラウドサービスやアプリがたくさんあります。
月々数千円から始められる施工管理アプリを導入しただけで、電話やFAXのやり取りがなくなり、残業時間が70%も削減された、という地方の土木会社もあります。
実際に、中小の建設企業に特化してDXを支援する企業も増えています。
例えば、テクノロジーで建設業界のアップデートを目指すブラニュー(BRANU株式会社)のような企業が開催するイベントに参加してみるのも、情報収集の素晴らしい第一歩です。
現場の声に耳を傾ける企業から直接話を聞くことで、自社に合ったツールや考え方のヒントがきっと見つかるはずです。
むしろ、意思決定が速く、小回りが利く中小企業こそ、DXの恩恵を最も受けやすいと言えます。
まずは小さな一歩から。
その一歩が、大手企業を凌駕する競争力に繋がる可能性を秘めているのです。
明日から現場でできる、DXへの小さな一歩
では、具体的に何から始めればいいのでしょうか。
ここでは、明日からでもあなたの現場で試せる、DXへの小さな、しかし確実な一歩を3つご紹介します。
1. まずはスマホアプリから!情報共有を変えてみよう
全ての基本は、情報共有の円滑化です。
まずは、無料でも使えるビジネスチャットツールや、建設業に特化した施工管理アプリをスマートフォンに導入してみましょう。
現場の写真を撮って、関係者に一斉に共有する。
それだけでも、「事務所に戻って報告書を作成する」という手間が省けます。
「あの件、どうなった?」という確認の電話も激減するはずです。
まずは、電話とFAXを一つでも減らすことを目標にしてみてください。
2. ドローンで現場写真を撮ってみる
「ドローンなんて大げさな…」と思うかもしれません。
しかし、数万円で購入できるホビー用のドローンでも、現場では絶大な効果を発揮します。
これまで足場を組まなければ確認できなかった屋根の状態や、広大な現場全体の進捗状況が、安全かつ数分で把握できるようになります。
何より、鳥の視点から自分たちの現場を見るという体験は、社員のモチベーションを大きく向上させます。
まずは一度、飛ばしてみる。その感動が、変化への第一歩です。
3. 「わからない」を共有する文化づくり
実は、これが最も重要かもしれません。
新しいツールを導入する際、必ず「使い方がわからない」「面倒くさい」という声が上がります。
その時に、「やる気がない」と突き放すのではなく、「どこが分からない?一緒にやってみよう」と寄り添う姿勢が、経営者には求められます。
経営者自身が率先して新しい技術を学び、その楽しさや便利さを語る。
社員の「わからない」という声を歓迎し、全員で解決策を探す。
そんな心理的な安全性が、DXという新しい家の頑丈な基礎工事になるのです。
まとめ
泥と汗にまみれた建設現場と、スマートなテクノロジー。
一見、相容れないように見えるこの二つが、今まさに融合しようとしています。
この記事でお伝えしてきたことを、最後にもう一度振り返ってみましょう。
- 建設業界は「2024年問題」や人手不足という待ったなしの課題に直面している。
- DXの真の目的は、効率化だけでなく、職人が誇りを持って働ける環境を取り戻すこと。
- BIM/CIM、IoT、AIといった技術が、現場のあり方を根本から変え始めている。
- DX成功の鍵は、高価なシステムではなく「現場の声」から始める小さな一歩にある。
私の親父が守れなかった会社。
その悔しさをバネに、私はこの世界に飛び込みました。
そして今、確信を持って言うことができます。
テクノロジーは現場を冷たくしない。むしろ“手のぬくもり”を残すための道具だ。
この記事を読んでくれたあなたが、明日、現場で何か一つでも新しいアクションを起こしてくれたら、それ以上に嬉しいことはありません。
難しく考えなくて大丈夫です。
まずはあなたのスマートフォンで、現場で頑張る仲間の写真を一枚撮って、「いつもありがとう」とメッセージを添えて、グループチャットに投稿することから始めてみませんか?
その小さな一歩が、あなたの会社と建設業界の未来を変える、大きな革命の始まりになるはずです。